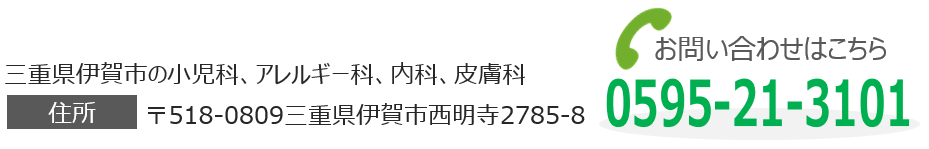牛が家族で会った頃
坂を上って、屋敷の東の門をくぐり、「ただいま」と言うと、首を出し草を食べている牛だけが大きな目を向け迎えてくれた。「まや」と呼んでいた八畳ほどの牛舎は、母屋の東南角にあった。
昭和三十年頃は、農家のほとんどは黒毛和種のメス牛を飼っていた。農耕や運搬に使用し、肉牛としても飼育した。えさは朝と晩に与えた。木の桶にイネワラを四センチほどに切って入れ、米ぬかやふすま、大豆カスなどを与え、さらに米のとぎ汁やなくの洗い水を溜めておき、牛専用のなべで沸かしたものをかけ、よく混ぜ、さまして与えた。
朝晩のえさの他にも、夏にはあぜや土手の青草を刈り取り与えたし、冬には干し草を食べさせた。牛は胃に入った食物をふたたび口に一戻してかみなおすのであるが、いつもモグモグロを動かしていた。
牛は一つ屋根の下で暮らす家族の一員であった。正月のもちつきには、牛のためにくず米の粉をむしてつき、「牛だんご」を作り、「牛の正月」といって、焼いてえさに混ぜて食べさせた。
健康にも気づかい、針を一本落としても牛が食べたら大変と大捜しで、釘の始末にも神経質であった。牛は異物をなめたり飲み込んだりする癖があり、釘など を飲み込むと胃壁を突き破り創傷性心膜炎を引き起こすという。
「かど」と呼んでいた家の前に、百五十センチほどの栗の柱が一本立っていた。牛つなぎの柱で、そこにつないで鞍をつけたり、ブラシをかけた。作業中はアブもよくたかつたが、耳をピクつかせ、尾を自在に振って追っ払っていた。
別れの時もこの柱につながれ、馬喰(ばくろう)」と呼ばれた牛買いが来るのを待った。売られていき、その後の定めを知っているのか、大きな澄んだ目は、視線があえばまばたきもして悲しげであった。父はなわをはずして馬喰さんに渡した。祖父母も父母も私も姉も言葉なく、ついに毎曰のえさやりをしている母が「さいなら」と言い、再び沈黙の中、牛は門を出て坂を下っていった。小学二年の私はうつ向き、右手の甲で二度三度目をふいた。
家畜は家族の一員といっても、最初から最後まで愛玩されるペットとは決定的に異なる。人間の都合で飼いならされて、人間の食用肉となるために命をも奪われる。
今の子供たちは、生きた牛を間近で見ることもなく、目にするのはきれいなパックの精肉で、生身の牛と結びつかない。スーパーのそれは、生き物と連想されないよう気づかつているようでもある。また以前なら肉屋へ行けば、皮をはぎ、骨が付き大きくばらされた牛がつるされているのが見えた。生々しく気持悪かつたが、その鮮烈な光景が子供心に染み込み、人が生きるための現実を知らしめた。
今やlT(情報技術)革命といわれ、家畜やペットを飼うどころか、仮想の世界で飼育する疑似体験ですましてしまう。ある者は、疑似体験を実体験と錯覚し、虚構を虚構と気づかぬようになり、精神をも変質させる。それを防ぎ、バランスよく生き抜くためには、幼児期少年期の生身の体験とその蓄積が不可欠で、昔以上に必要と一言える。しかし、それも親や学校が意識して機会や場を与えなくてはならぬものとなった。
我々は危うい時代を生きている。