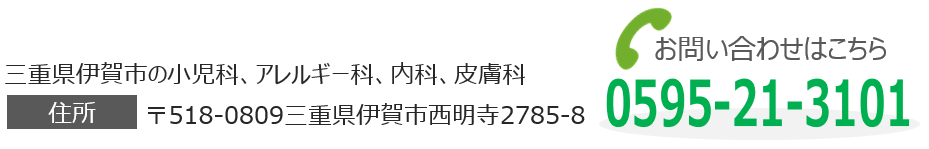山の神
今日一月七日は、「山の神」の曰である。 家の男たちは山の祠にお参りし祭祀を行う。私も十八歳まで毎年加わっていた。「さあ行くぞ」と父は幼い私に声をかけ、 祖父と三人で家を出る。外はまだ暗い。雪の山道を東に進む。サクサク雪を踏む足音と息づかいだけの静寂。時にガサッと枝より落ちる雪の音。 途中、父は数日前に雑木の枝を四~五本束ねて作った「カギ」をかつぎ、祖父は新しいわらを持っている。私はお供えのもちの入った布袋を背負うが、子供の肩にけこう重く、もう少し、自分の役割と耐えて いた。
曲がりくねった道を一Kmほど進み、最後 の約百メートルは急な松林を登る。幼児期 にはおんぶされ、そして手を引かれ、長するに従い自力で登れるようになる。しんどい思でやっとのものが、次の年には難なく登れ、一年間の身体の成長を実感できた。
山腹の十坪ほどの広場につけば、まず小さな石の祠の前で礼拝し、もちを半紙の上に重ね、さらにミカン、たつくり、くし柿を置く。二人三人と各家の男たちが登ってくる。おめでとうございますとあいさつが交わされ、全員がそろうと、しめなわ作りが始まる。持ち寄ったワラを一にぎりづつ差し込み、ねじり、手際よく作られていく。御神体の前の二本の木の間に張られた五メートルほどのしめなわに、八戸の家のカギがかけられ、ヨイショヨイショとカギを引く。あっけなく切れる年や、なかなか切れない年もある。
かぎ引きが済めば、まわりはすっかり明るくなっている。たき火を囲み、御神酒をいただく。当番の家の重箱さかなが回され、木の枝につきさしもちを焼く。焼いたもちはもって帰って七草粥とともに家族でいただいた。
酒も入りなごやかな談笑となる。子供にとり村の長老の話を身近に聞く年に一度の機会でもあり、その話しぶりや笑わせ方に年季を感じた。炎や煙の向こうにみる老人たちの顔は、人生の苦楽が織り込まれて存在感があり、火に照らされて大きく見えた。今でも薪能の場面のごとくよみがえる。森田のじいさん、磯田のじいさん、上野のじ いさん、みないい顔であった。何かと目をかけてくれたがもういない。
家に男児が生まれれば、酒一升を供えるのがならわしで、新しいメンバーとなる。 消えた顔があり、新しい顔がある。この祭祀の集まりに、小学生の私は世代の交代というものをある種、恐れをもって感じていた。またこの集まりは、目上の人や長老に対する言葉遣いや態度をまのあたりにして修得してゆく機会でもあった。祖父に対する青年の振る舞いに、地域における祖父の存在を知る事もできた。
今思うに、山の神々をまつる講の神事ではあるが、大切な教育的役割も持っていた。伝統行事は簡略化され、または興業的となりすたれてゆくものも多いが、付随して地域の教育力も失われてゆく。個人主義的な、そしてインターネットや電脳の現代にあってこそ、幼児期からのface to face(顔と顔と向き合った)の地域での教育が一層重要であると思えてならない。