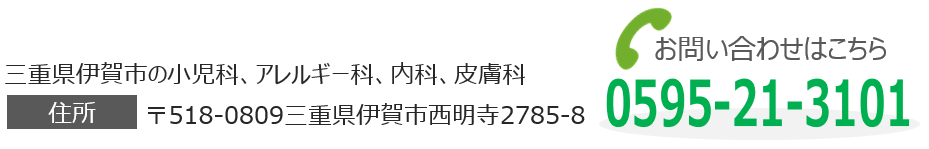極端事例に患う
他県で暮らす若い夫婦も、夏休みには子どもを連れて帰ってくる。孫の姿を見るや、「これ何」と祖父母はびっくりし、こちらの病院でも診てもらったらと勧める。まずは素直に聞き入れて連れてくる。 四ヶ月の女児で第一子。手足の動きは活発だが、肋骨が見えるほどにやせている。生下時二千九百二十gもあったのに、まだ四千四百八十gしかない。母親も母乳が足りず,それが原因だと分かっている。「○式母乳保育」に共感し、実践している。母乳は多少とも出ており、命に別状はないが、栄養失調の状態でも、なおミルクを足すことなく母乳だけに固執している。母親の知能が低いからでも、経済的理由からでもない。知能は高い。父親は「そらみろ、おれの言った通りだる」と大声を出すわけでもなく、じっとやりとりを見つめている。同じ考えの同志なのかもしれない。
次の例は、十ヶ月の男児だが、顔一面が赤く腫れあがり、細菌の二次感染をも来たしひどい湿疹。よくもここまでに至らしめるとは。病院はステロイド軟こうを使うからと避け、「○水療法」に、遠くの施設まで熱心に通い、多額の費用もかけている。よくなればそれでよいのだが、この例では極度に悪化しており、「ステ□イド恐怖」の母親が必要な治療を阻んでいる。
近頃、このようなケースにしばしば出会う。その背景に、親、特に母親に漠然とした不安があるように思う。「母乳で抵抗力のある元気な子に育てたい」「恐ろしい薬害から守りたい」「親の私が今してあげなくては」という思いが、不安に増強されている。 そして的確な判断を欠き、 特定の情報に取り込まれ、 呪縛されてしまう。それは強固で、時間をかけた説明でもなかなか解けない。先のアトピー例も、名古屋へ帰った今も、変わらず水療法だけを続けているという。
母親のかぜ薬を処方する際、服用中の薬を問えば、抗不安薬を示す人が意外と多い。また睡眠薬おいていますかとよくたずねられる。こうしてストレスに耐えている大勢が、極端例の背後にいるのである。
経験する極端例は、核家族に多く、家族形態も関係している。同居にはそれゆえの日々のあつれきはあるけれど、子育ての点では、みんなが助けてくれるという安心感があり、母親の緊張もその分ないし、家族の意見も受け入れやすい。限度を超えたとき、「そんなことしていてはダメ」と強く、生活を共にする家族だからできる介入がある。そうして手遅れや極端が防がれている。核家族であれば、曰々のわずらわしさはないが、その分、外来で診ていても祖父母とは会話の中にも距離がある。若い母親なりに懸命に育てているのだし、「こんなことしていてはダメ」と介入できる距離にない。また同居でないのでその介入のタイミングもとりにくい。一度こちらの病院で診てもらったらと勧めるのが精一杯である。大家族が持つ一体感や帰属感は、カウンセリングや抗不安薬がなくても現代を生きていく上で、大きな役割を果たしていると思えてならない。核家族で暮らすにせよ、この点を意識していた方がよい。
「仕事は先進的に、生活は保守的に」この言葉、ふいにではあるが、しばしばうかぶこの頃である。
2001年8月