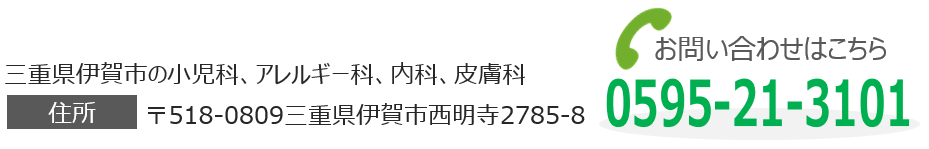熱性けいれん
先程インフルエンザで診察したばかりの子供だが、帰宅後すぐにひきつけた。子供は、急に高熱をきたしてよく熱性けいれんもよく起こす。
熱性けいれんは生後6ヶ月から5歳位によくみられます。
およそ100人に5人の子供が経験し、1度起こした子供の半数は再度起こします。ひきつけやすい遺伝的な要素もあるようです。
発作は全身性のもので、突然体を硬直させ手足をつっぱり、頭を後ろにそらせます。
目は一点を凝視し呼吸は苦しそうですが、このため窒息することはありません。
大部分は5分以内におきまり、発熱が続いても再度ひきつけることはまれです。
後遺症を残すことなく、歩けないとか、筋力低下をきたすことなどもありません。脳波も正常です。
多くの熱性痙攣は、このような良性のもので5~6歳までに治ってしまう心配のいらないものです。
てんかんや他の病気が考えられる、心配すべき熱性痙攣は以下のような、典型を外れた場合です。
①けいれんが二十分以上続く
②1曰に何回も起こす
③体の片方や一部分だけのけいれん
④発達の遅れや神経の病気が在る
⑤生後6ヶ月迄に、又6歳を過ぎても起こる
⑥熱がないのに起こしたことがある
これらの一つで当てはまれば、たとえ1回の痙攣発作でも詳しい検査が必要です。
発作の対応ですが、
1. あわてない:たいていのひきつけは手当をしなくても通常5分以内に止まります。また痙攣そのもので命にかかわることはまずありません。
2. 口の中に割り箸などを入れない:傷をつけたり無理なこじ開けが刺激になります。また動転した親が体を揺りますが、これも刺激となりよくありません。
3. 楽な姿勢で誤飲を防ぐ:安全な場所に移し、衣服を緩め、吐いたものがのどや気管につまらないように横向きに寝かせます。
4. 観察する:時計を見て痙攣発作がどのくらい続いているか確かめ、診察のとき話せるようにします。
5. 熱を下げる:解熱用座薬があれば、指示された量を使う。また、アイスノンや熱さましのゲルつきシートも使ってよい。
6. 病院受診:痙攣が10分以上つづく場合は救急受診が必要です。通常の熱性痙攣なら発作がおさまってから、あるいは翌日診察を受け、脳波検査のことや、痙攣予防の薬に使い方など指示を受けます。
熱性痙攣は、心配ないとはいえ防げるものなら防ぐべきです。
繰り返し起こす子供には発熱初期に痙攣予防の薬を使います。
発熱に気づくのが遅く予防の薬を使用するまでに、痙攣を起こしてしまうこともありますが、前もって指導しておくとそこは母親、発熱の前兆に気づき適宜の使用でかなりうまく防げます。
「ピーポー、ピーポー」と救急車のサイレンが近づいてくる。いくつになってもこの音には反射的に身構え、緊張するものです。